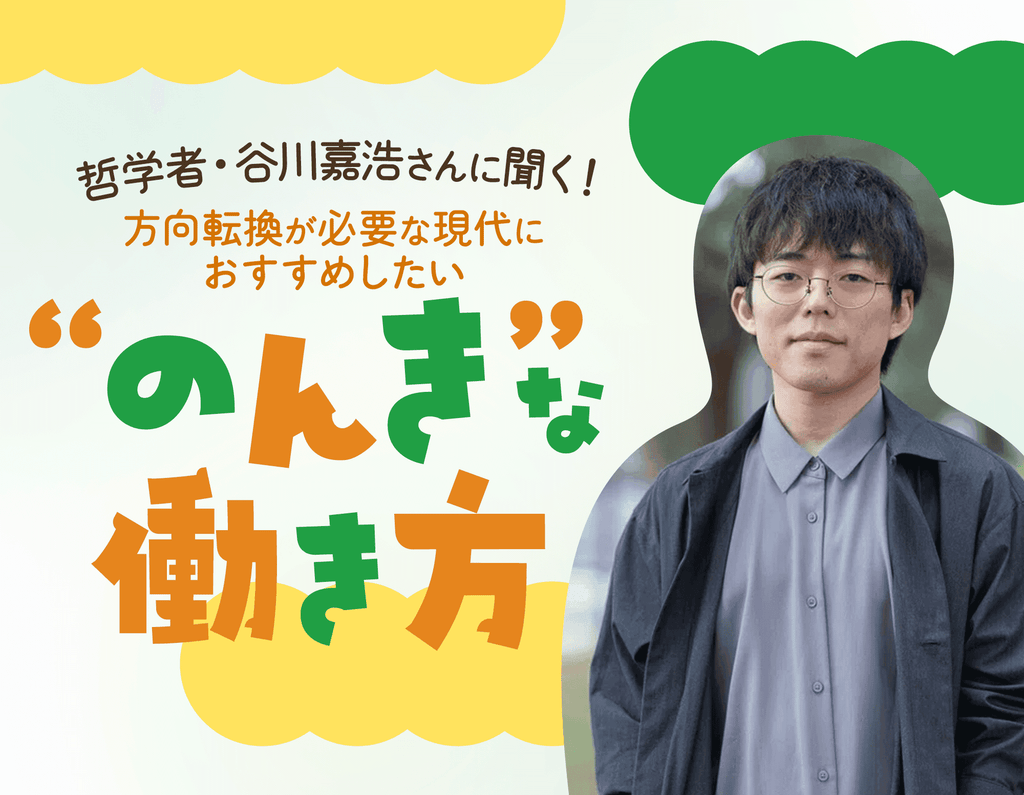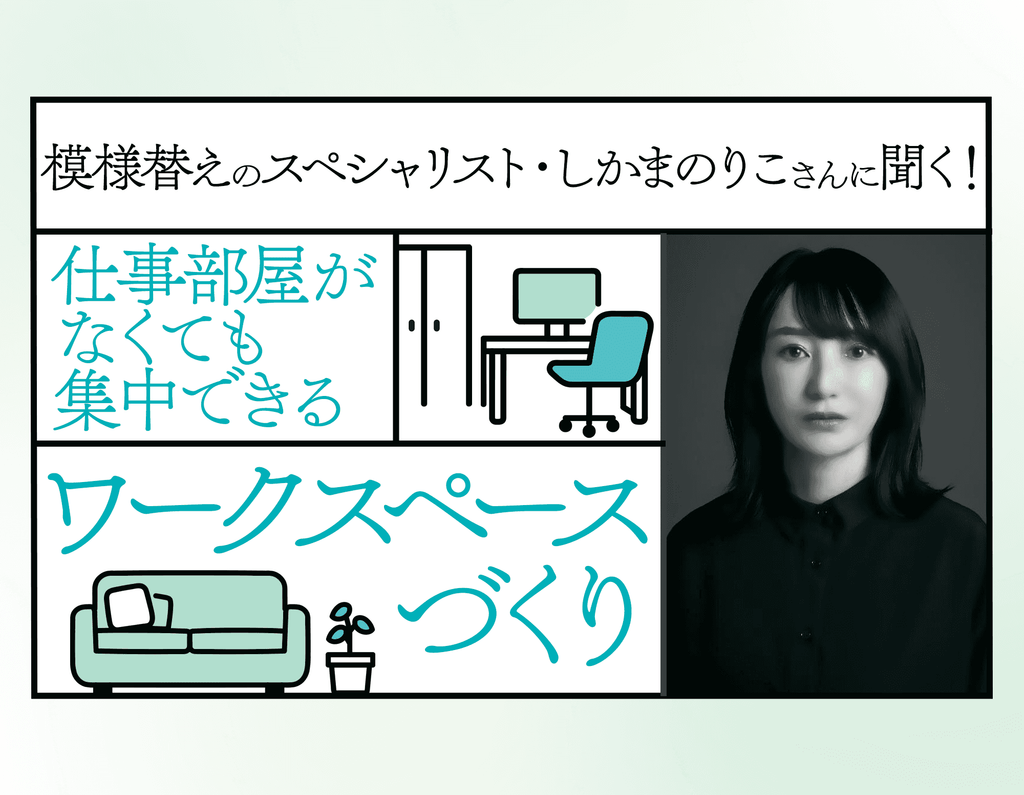親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かした事がある。なぜそんな無闇をしたと聞く人があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。新築の二階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張っても、そこから飛び降りる事は出来まい。弱虫やーい。と囃したからである。
「在宅ワークになってから、朝起きられなくなった」「ダラダラ仕事をして、遅寝遅起きになってしまう」……そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
自分で時間をコントロールできる在宅ワークは便利な一方で、始業寸前まで二度寝を繰り返してしまったり、ダラダラと夜まで仕事をして夜更かしが習慣になってしまったりと、朝に余裕がなくなる原因にもなります。
今回は、『「朝4時起き」で、すべてがうまく回りだす!』(マガジンハウス)の著者であり、朝活の第一人者として講座や執筆活動を行っている池田千恵さんに、無理なく取り入れられる朝活のコツを伺いました。
朝活とは「始業前に自分の時間をつくること」
一日のはじまりである朝の時間帯に、勉強、運動、趣味などの活動を行う朝活。脳も体も疲れきった夜ではなく、脳が一番活性化する朝に作業することで、効率よく進めることができます。実際、私も夜1時間以上かかっていた作業が、朝やるとたった15分で済んだことがありました。
しかし、実は朝活の一番のメリットは、朝から「自分で決めたこと」をやって達成感を得られることです。一日のはじまりに主体的な時間を取ることで「自分の人生を生きている」感覚を得ることができ、そんな日々の積み重ねが自信や自己肯定感を形成していきます。
だから朝活は、「早朝に起きる」ことが本質ではありません。早起きできなくても、始業前に自分主体の時間を持てれば、それは朝活です。私は『「朝4時起き」で、すべてがうまく回りだす!』という本を書いてはいるんですけど、必ず朝4時や5時などに起きるべき!と推奨しているわけではないんです。

「朝活をしたいんですけど、在宅だとなかなかできなくて」――そういった相談を受けることはよくあります。
オフィス出勤の場合は、通勤時間や始業時間など、外部で決められた時刻があります。それに間に合うように逆算して、朝起きる時間や身支度をする時間といった「自分の生活リズム」もできあがります。ところが在宅になると強制力がなくなり、そのリズムがすっぽり抜け落ちてしまいがちです。極端にいえば、始業の直前まで眠っていても仕事を始められてしまう。また、夜更かしして朝起きられない、起きられないからまた夜更かしする……そんな悪循環に陥りやすいんです。
こういった悪循環の状態からいきなり早朝に起きて朝活しようというのは無理があります。だからまずは、いつもより1時間早く起きてみて、その時間を自分のために使ってみてください。そうすればきっと、そのぶん夜に時間を使わなくてよくなってくるはずです。
Have toとWant toを組み合わせて朝活を有意義に
単に早起きをするでは朝活とは言えません。だらだらスマホを見て終わったり、眠くて作業がはかどらなかったりしたら、達成感どころかガッカリする結果になってしまいます。せっかく早起きしたのに、もったいないですよね。
そこでおすすめなのは、家事や仕事などの「やらなければならないこと(Have to)」と趣味や勉強などの「やりたいこと(Want to)」をセットにして行うことです。
Have toだけだと義務感が強くモチベーションが下がりますし、かといってWant toだけだと達成感が得られにくくなります。だから私は朝活の前半でやらなければならないことを済ませて安心してから、やりたいことを楽しむようにしてるんです。両方行うことに意味があるので、もちろん逆の順番でも構いません。「起きたらやりたいことをやるぞ」と思いながら早起きを目指すのもいいですよ。

とはいえ、頭の働かない朝一番から「何をやるか」考えるのは億劫なもの。前日の夜に、朝どう動くかイメージしておくとスムーズです。特にやりたいことはたくさんストックしておくといいでしょう。時間があるときにノートに「好きなことを100個」書き出してみると、必ずいくつか朝活で取り入れられることが見つかるはずです。読書や散歩、コーヒーを丁寧に淹れる、録りためたドラマを一話見る……些細なことでも構いません。思いつくままどんどん書いてみてください。
義務的な行動だけで時間を埋めず、自分主体で気持ちよく一日を始められる有意義な朝活を続けてみましょう。
夜型の人は「早起き国」に留学する気持ちで
夜型だからといって、朝活を諦める必要はありません。
夜型の人が朝活を始めるときに、まず忘れてはいけないのは「睡眠時間を削らない」ことです。自分には何時間の睡眠が必要なのかを、2週間ほど記録して俯瞰してみましょう。そのうえで、必要な睡眠時間を確保できるよう生活を整えていくことが、朝活の前提になります。
とはいえ、夜更かしが習慣になっていると、急に早寝をするのは難しいもの。夜型の人は「早起き→早寝」の順で生活を変えていきましょう。最初は眠くても、まず早起きをする。私はこれを「早起き国に留学する」と呼んでいます。留学したての頃は時差ボケで眠いのが当たり前。その感覚で少しの間がんばると、体のリズムが少しずつ整っていきます。
一方で、仕事や家族の事情で夜型が避けられない人もいるでしょう。その場合は、無理に平日に朝活を取り入れようとせず、週末だけ朝活を取り入れてみるのもひとつの方法です。土曜日は疲れもあるでしょうからゆっくり朝寝坊してOK。そうしてしっかり休んだ翌日の日曜は早起きにチャレンジして、新しいことをやってみましょう。近所の朝市へ出かける、行ったことのない喫茶店のモーニングを楽しみに行く、休日朝の人気がない静かな時間に散歩をする――そんなふうに休日の朝を「自分の時間」として楽しむだけでも、生活に新しいリズムが生まれます。
できない日があっても365日朝は来る
朝活をし続けたくても、体調不良や飲み会などで、どうしてもできない日は絶対にあります。私自身も、子どもが生まれた直後は、子育てで朝活が途切れてしまいました。
そういう時期は「この時期が終わったらやろう」と思ってしまう人が多いでしょうが、「この時期」が終わったらまた次のことがやってきて、ずるずる朝活ができなくなってしまいます。むしろ、そういうときでも続けられるよう意識し工夫するのが大切です。
繰り返しになりますが、朝活で大切なのは「一日のはじまりに自分で決めたことをやる」ということです。だから、朝活のハードルは自分でコントロールしてOK。大変な時期はハードルを下げて「できた」と思える日を増やしてみるのもおすすめです。
たとえば、私は朝活を「松竹梅」に分けています。松は「前日に、朝やると決めたことをすべてできた状態」、竹はその半分は達成できた状態、梅は「ただカーテンを開けて日の光を浴びる」など。できた/できないの二元論ではなく、グラデーションをつくっておくことで、「今日は全然できなかった」と落ち込むことがなくなり、「梅は続けられているからOK」「今日は竹までできた!」というふうに自己肯定感を育んでいけるのです。

どうしても無理なときは、思い切って休んでしまっても大丈夫。ただし、自分で主体的に休むと決めること。私は「戦略的二度寝」「戦略的休息」なんて言葉を使います。自分で自分をちゃんとコントロールしたうえでの朝寝坊であれば、次の日からまた気持ちを新たに朝活に取り組むことができるはずです。
365日、必ず朝はやってきます。今日できなくても、また明日から始めればいいのです。
朝活で自分が舵を取る一日を始めよう
朝活は、無理やり早朝に起きることでも睡眠時間を削ることでもありません。大切なのは「自分だけの時間」を持つことです。会社のため、家族のためと、誰かにスイッチを押されるのではなく、自分で一日のスイッチを入れる。その主体的な感覚こそが、朝活の本質だと思います。
私にとって朝活は、自分の人生を生きるためのスタートボタンのようなもの。毎朝、生まれ変わったような気持ちで一日を始められると、自然と仕事も生活も前向きに進んでいきます。
自分のリズムをつくる第一歩として、まずは朝に少しだけでも自分のための時間を用意してみてください。明日の朝が、あなた自身の手で押す新しいスタートボタンとなりますように!
池田千恵
株式会社朝6時代表/作家
朝時間を活用したライフスタイルを提案し、講演や執筆、企業研修など幅広く活動。朝専用手帳『朝活手帳』をプロデュースし、朝活の実践法を伝えている。著書に『ME TIME 自分を後回しにしない「私時間」のつくり方』(ディスカヴァー)、『週末アウトプット』(日本実業出版社)など。
取材・執筆=いわさきはるか アイキャッチ・図版=サンノ 編集=モリヤワオン(ノオト)

ブランド名
商品名が入ります商品名が入ります
¥0,000