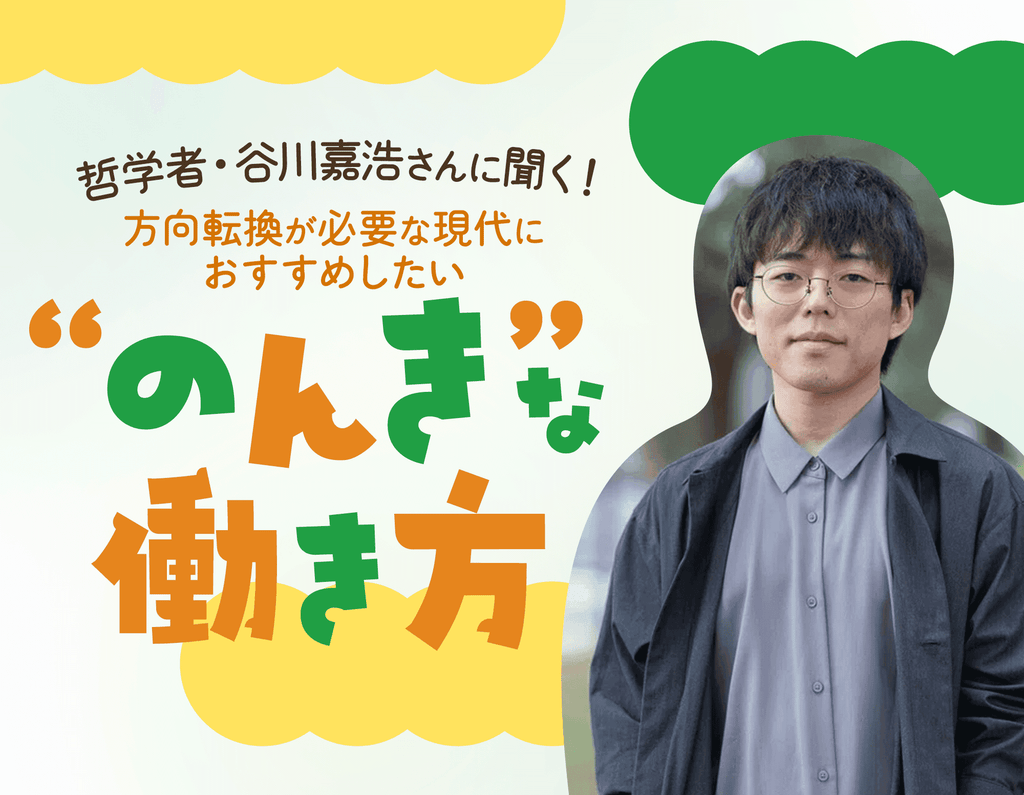親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かした事がある。なぜそんな無闇をしたと聞く人があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。新築の二階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張っても、そこから飛び降りる事は出来まい。弱虫やーい。と囃したからである。
在宅ワークをしている人にありがちなワークスペースの悩み。「リビングで仕事をしていると、家族の気配を感じて落ち着かない」「一人暮らしで部屋が狭く、どこにワークスペースをつくるべきかわからない」など、どんな生活状況でもモヤモヤは生じてしまうものです。
そこで今回は”模様替えのスペシャリスト”としてテレビや雑誌に多数取り上げられる一級建築士・しかまのりこさんにインタビュー。「在宅ワークでも仕事に集中できる部屋のレイアウト」について解説してもらいました。
快適なワークスペースをつくるための基本原則
仕事専用の部屋がない家では、家族で共有するリビング・ダイニングの一部や、ワンルームの一部などをワークスペースとして活用することになります。しかし「なんとなく」でワークスペースをつくると、仕事用品とそれ以外のモノが入り混じったり、行き来がしづらくなったりしがちです。
そこでぜひ取り入れてほしいのが、ワークスペースをつくりたい部屋を「仕事をする」「食事をする」「くつろぐ」といった機能ごとに「空間分け」する考え方です。そのうえでそれぞれの空間に専用の収納をつくれば、モノが入り乱れることもなくなります。
空間分けの際には、動線、つまり人やモノが空間を移動する経路を考えて家具を配置することも大切です。家具と家具のあいだは、最低でも60センチから70センチは開けましょう。それより狭いと、たとえば「いちいち椅子をどかさないと通れない」といったことが起こり、居心地の悪い部屋になってしまいます。もしこれから模様替えをするなら、先に空間分けをしたあと、空間に適した大きさの家具を選ぶのがベストです。
また、ワークスペースには、長く過ごすのに適した環境を選んでほしいですね。換気と温度管理ができない場所はNGです。例えば、押入れや物置部屋などは窓がないので、二酸化炭素濃度が上がって頭がぼんやりしてしまいます。廊下など、冷暖房がない場所で仕事をするのも、快適さを欠き集中力も続きにくいため避けましょう。
狭い部屋では「動線の確保」を特に意識
ここからは、実際に私が模様替えをお手伝いした部屋を例にレイアウトのコツを解説します。
まずは、ワンルームや1Kなど一人暮らし用物件のレイアウトです。
■ワンルーム
こぢんまりとしたワンルームでは、動線の確保を意識して、各スペースに行き来しやすくすることが大切です。まずは、ベッドを壁に沿って置き、頭とは反対側の壁にデスクをくっつけてワークスペースをつくってみます。仕事用品は、デスクサイドのデスクワゴンに片付けましょう。

ゆったり広々とはいきませんが、「仕事をする」「食事をする・くつろぐ」「寝る」という3つの機能ごとに空間が分かれており、それぞれのスペースに行き来しやすいレイアウトになりました。食事はワークスペースでとることもできますが、食事専用のスペースをつくった方がオンオフの切り替えがしやすくなります。
自由に使える空間を増やしたいなら、ベッドを縦に置くこちらのレイアウトもおすすめです。ただし、クローゼットの扉がベッドに当たって開閉しにくくなるため、扉を外す必要があります。

扉は自力で簡単に外せますが、賃貸物件の場合は必ず大家さんや管理会社に許可をとってください。また、退去時には原状復帰が必要です。
■1K
ワンルームより少し広い1Kでは、間仕切り収納をうまく使うことで、コンパクトな空間に「仕事をする」「食事をする・くつろぐ」「寝る」の3つの機能を同居させることができます。

気をつけたいのは、間仕切り収納の高さです。高すぎると倒れる危険があるので、だいたい120センチ程度のものを選ぶといいですね。
二人暮らしでは、お互いの気配を感じないよう部屋を分ける
同棲カップルや子どものいない夫婦などの二人暮らしに多い、2DKの間取り。在宅ワーク中にお互いの気配を感じず仕事に集中するには、くつろぐスペースとワークスペースをきちんと分けるのがポイントです。
■2DK
このレイアウト例では、ダイニングと1人のワークスペースを兼用し、DK横の1部屋を2人でくつろぐためのスペースにしています。

一人は寝室で、一人はダイニングテーブルで仕事をするため、ダイニングの椅子はワークチェアを使っています。省スペースのため一脚の椅子はテーブル下に収納できるスツールなどにして、揃って食事するときだけ出すのもいいですね。
リビングで仕事をするなら、くつろぐ場所に背を向ける
お子さんのいるご家庭でのレイアウト例も見ていきましょう。
■ファミリータイプ①
こちらは、ファミリータイプの物件のLDK部分です。横長リビングで12~13畳と比較的広さがありますが、仕事をするとなると家族の気配が気になったり、モノがごちゃついたりしがちです。
そこで、壁にデスクを沿わせてワークスペースをつくります。このときにダイニングテーブルを横向きにすると、ワークスペースに行き来しやすくなります。

食事をするスペースやくつろぐためのスペースに背を向けているので、余計なものが視界に入らず仕事に集中しやすいはずです。仕事用品は、壁付けの棚や足元のデスクワゴンに片付けましょう。
■ファミリータイプ②
在宅ワークをする人が複数いる、子どもにリビング学習をさせたいといった場合は、ワークスペースを増やす必要があります。横幅が広いデスクに並んで作業してもいいですが、集中できない人もいるでしょう。その場合は、こんなレイアウトがおすすめです。それぞれのデスクが壁を向いているので、家族の存在が気になりません。

ワークスペースを複数つくることでダイニングセットを置く場所がなくなったら、このレイアウト例のようにダイニングソファを使って、食事スペースとくつろぎスペースを合体してしまうのもおすすめ。
ダイニングソファは一般的なソファとは違い、食事をするのに適したつくりになっています。座面が高く、硬めで体が沈みこまないため、姿勢を保ったまま食事をすることができます。
■ファミリータイプ③
タワーマンションに多いのが、LDKが正方形に近いこちらの間取りです。
ダイニングテーブルをキッチンカウンターにくっつけ、背中合わせになる位置にデスクを置きます。

ポイントは、ワークチェアを食事と仕事に兼用し、椅子の数を増やさないこと。くるっと後ろに回転させれば、そのまま仕事に使えるようにするのです。
「ダイニングチェアを使えばいいのでは?」と思うかもしれませんが、私はおすすめしません。仕事にも使うのであれば、やはり座面の高さを変えられて背もたれに遊びがあり、キャスターがついたオフィスチェアを選ぶのが正解です。「ダイニングにはダイニング用を」という固定観念は捨てましょう。
ダイニングテーブルを動かして生まれた空間は、ソファとラグを置き、家族団らんのスペースにします。「仕事をする」「食事をする」「くつろぐ」の機能ごとに空間が分かれた、メリハリのあるレイアウトになりました。
いずれにしても大切なのは、家族の生活スペースと、お仕事スペースを離すこと。部屋が分けられなくても、人があまり行き来しない場所にワークスペースをつくれば、集中しやすくなるはずです。
自然光が入る場所なら、さらに集中力アップ
空間を機能ごとに分けてそれぞれ専用の収納をつくり、動線を意識して家具を配置すれば、どんな部屋でも仕事に集中できるワークスペースをつくることができます。同居する人がいる場合は、人が出入りする機会が少ない壁際などにワークスペースをつくるといっそう集中できます。
また、人間は白い光の下で作業すると集中力が高まるため、自然光が入る場所にワークスペースをつくったり、白い光で照らすデスクライトを使ったりすると仕事の効率がアップします。これから模様替えする人は、こうしたポイントをぜひ意識してみてください。

しかまのりこ
模様替えアドバイザー/一級建築士
家具配置プランなどを提供するCOLLINO一級建築士事務所代表。テレビや雑誌など多数のメディアに出演するほか、セミナー開催や書籍の執筆も。著書に「狭い部屋でも快適に暮らすための、家具配置のルール」(彩図社)など。
執筆:小晴 図版:しかまのりこ アイキャッチ:サンノ 編集:モリヤワオン(ノオト)

ブランド名
商品名が入ります商品名が入ります
¥0,000