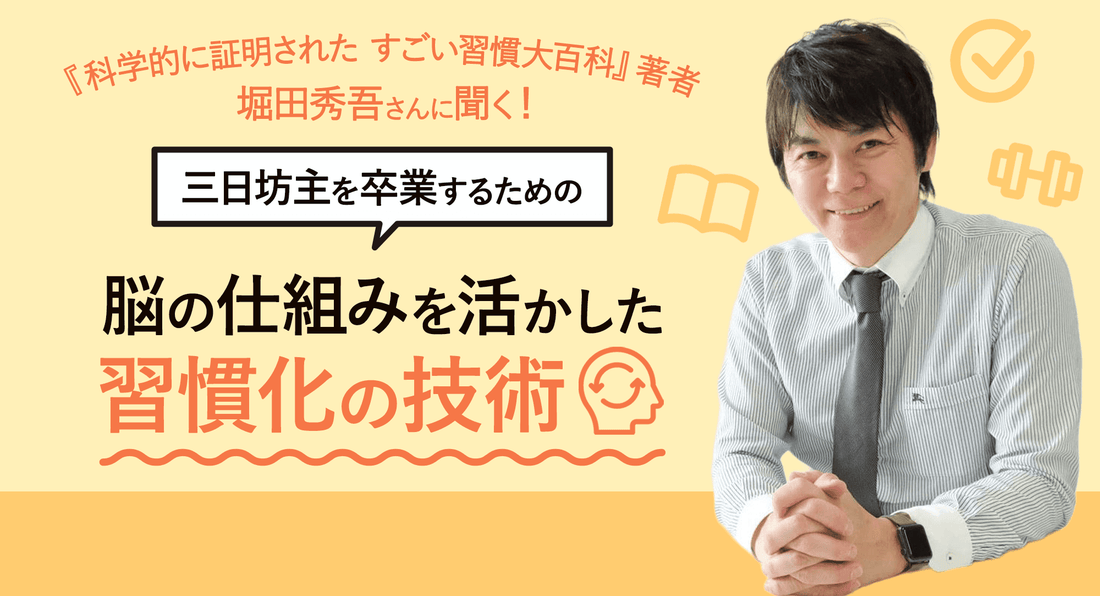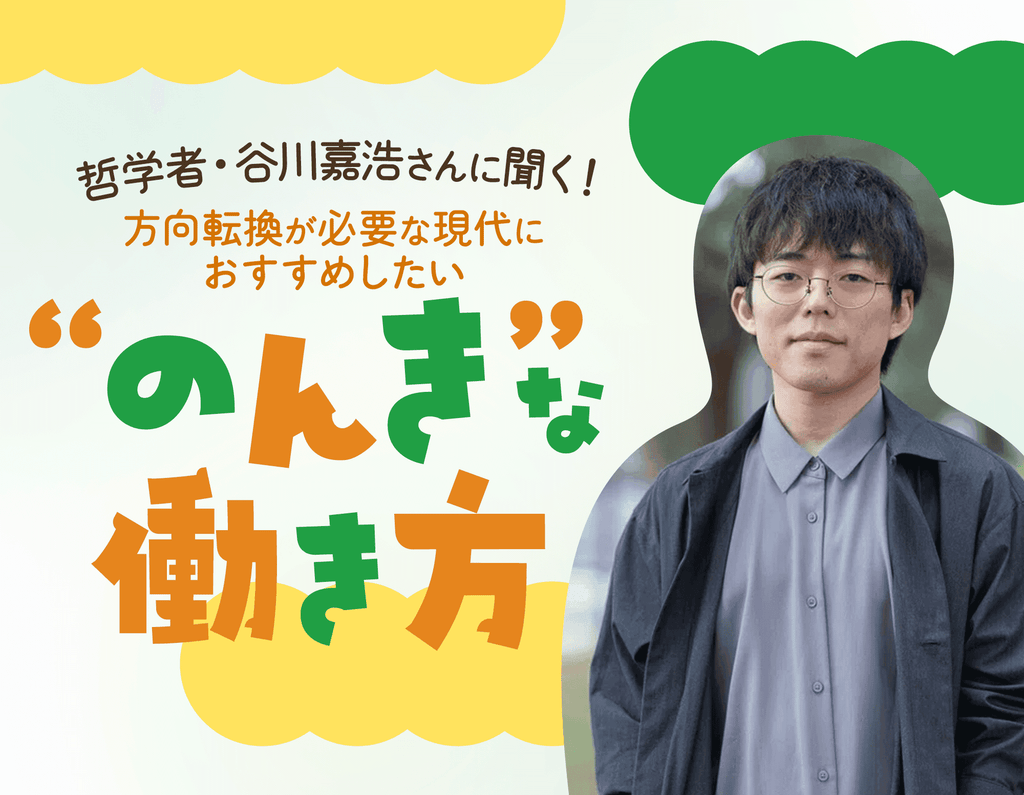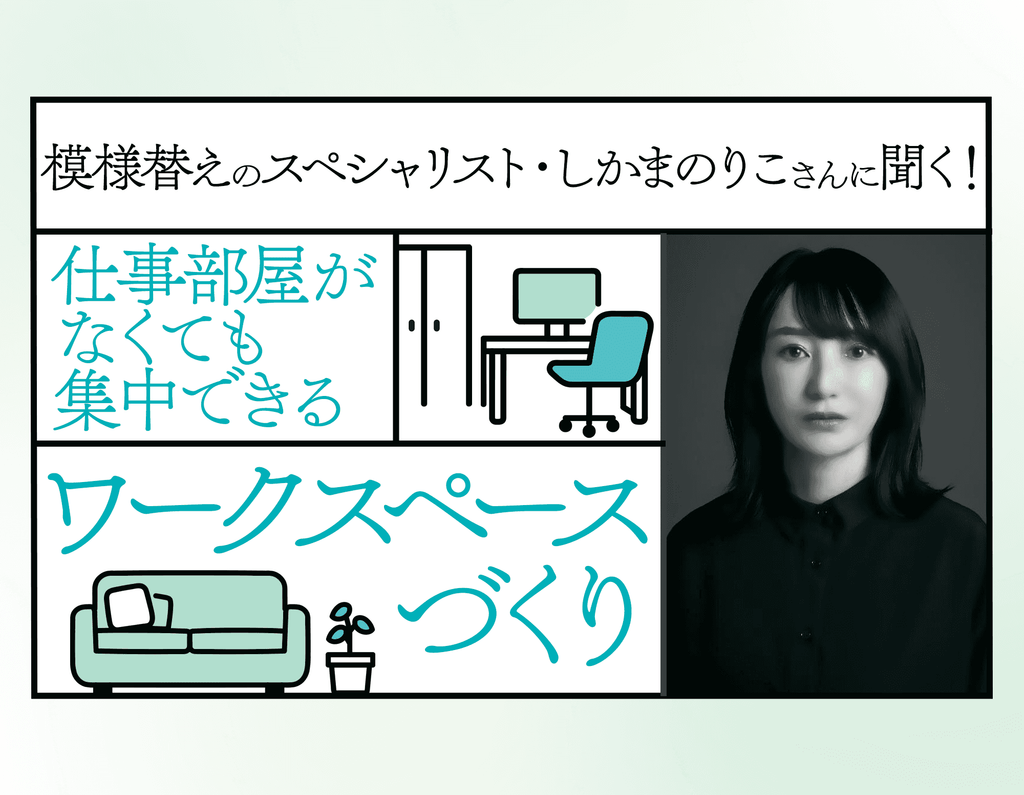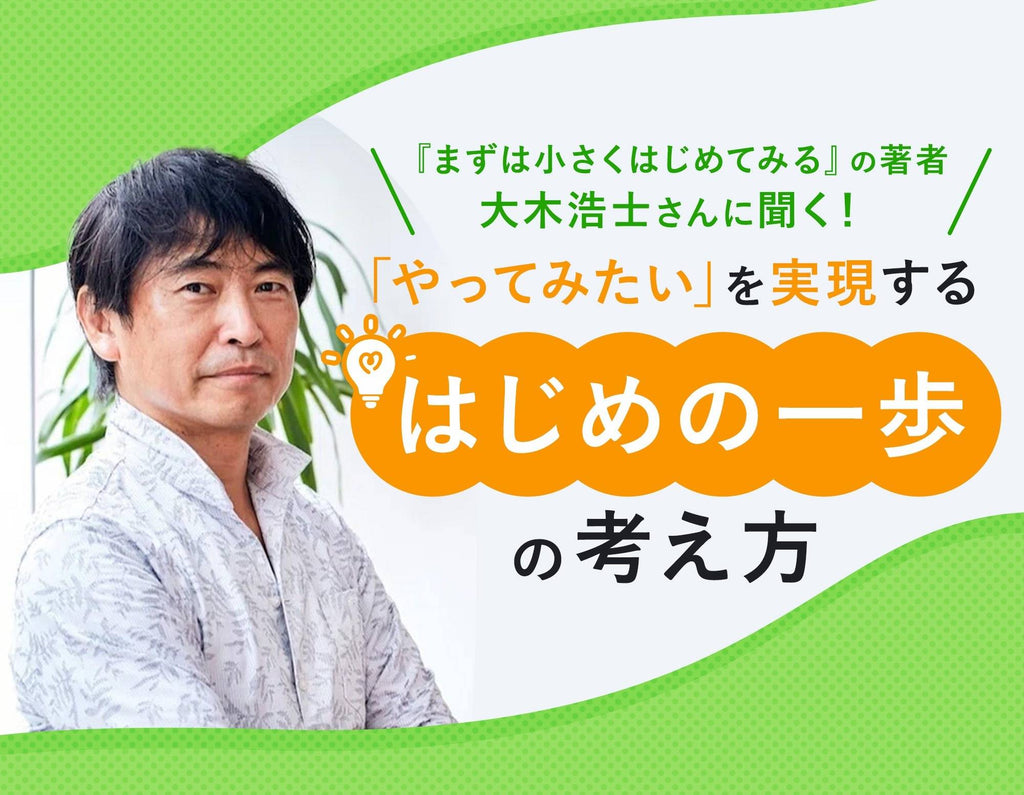親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かした事がある。なぜそんな無闇をしたと聞く人があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。新築の二階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張っても、そこから飛び降りる事は出来まい。弱虫やーい。と囃したからである。
勉強、筋トレ、読書など、毎日取り組みたいことはあれど三日坊主……という社会人は少なくありません。今度こそ習慣にしよう!と意気込んで買った参考書やスポーツウェアがいつの間にか部屋の片隅に置きっぱなしになっている人も多いのではないでしょうか。
仕事や家事などに追われる生活を送りながら、新しいことを継続するのは難しいものです。では、忙しい毎日の中に、やりたいことを定着させるためにできることとは? 『科学的に証明された すごい習慣大百科』著者で言語学者の堀田秀吾さんに、生活に取り入れやすい工夫やその技術についてうかがいます。
三日坊主には「メカニズム」がある!? 知っておきたい人間の本能
多くの社会人が、一度は「三日坊主」を経験したことがあると思います。やろうと思ったことをなかなか続けられず、「自分は意志が弱い」「また挫折してしまった」などと落ち込んでしまう人もいるでしょう。
そんな人にまずお伝えしたいのは、「習慣化できないのは、意志が弱いからではない」ということ。三日坊主には、「メカニズム」があるのです。
人間は基本的に飽きっぽい生き物です。新しいことを始めるときは刺激的で楽しく感じても、数日も経てば慣れるとともに飽きてしまいます。これは、同じ刺激を繰り返し受けると反応が薄れていく「馴化(じゅんか)」という作用によるものです。「馴化」が起きると、新しいこともつまらなく感じ、日課になる前にやめてしまうのが三日坊主のメカニズム。これは本能であり、その人の意思が弱いからではありません。

逆に、「馴化」を乗り越えて新しいことを完全に習慣化すると、その行動をしないと不安になったり、そわそわした気持ちになったりします。人間は同じ状態を維持することで、安心する本能があるからです。服を着る、歯を磨くといったことと同じレベルの行動になっていきます。
では、どうしたら新しいことを生活の一部にできるのでしょうか。日常に取り入れる工夫や技術を解説していきたいと思います。
習慣化のコツは、「脳の仕組み」を活用すること
ポイントは、人間の脳に備わっている「仕組み」を使うことです。本来、人間の意志は弱いので、気合いや根性で乗り切るのは至難の業。脳の「仕組み」をうまく使い、その行動を自然と続けざるを得なくなる「習慣化の原理」を3つご紹介します。
①まず動く
人間は、「やる気が起きたから行動を始める」のではなく、「動いた後でやる気が湧いてくる」生き物です。
人間は、体が先に動き出し、後から心が動く性質があります。カリフォルニア大学の生理学者であるベンジャミン・リベットの研究では、体を動かす脳の信号は、動かそうとする意思の信号より0.35秒早いことがわかっています。これは、動き出すことで脳の側坐核(そくざかく)と呼ばれる部位が刺激され、エンジンがかかる仕組みがあるからです。
これをうまく活用し、やる気が出るのを待つのではなく、先に動いてしまいましょう。
②ハビットスタッキング
すでに毎日している行動に、新しい行動を紐付けるテクニックです。「歯磨きをしながら、スクワットを10回やる」「子どもを習いごとへ送るついでに、近くのジムに通う」など、いつもやっていることに新しい行動を付け加えることで、継続しやすくします。
コーヒーを飲む、シャワーを浴びる、など毎日やっているルーティンをリストアップして、新しく始めたいこととどう紐付けられそうか、ぜひ考えてみてください。
③環境をデザインする
「やらざるを得ない環境」を用意することも大切です。人間の行動は、私たちが考えている以上に環境に左右されるものです。
たとえば、私が仕事用に使っている椅子には、キャスターが付いていません。あえて動かしにくい椅子にすることで、立ち上がってサボらないようにしているのです。椅子を動かすのが面倒に感じて「仕事をやらざるを得ない環境」をつくり、集中してタスクを終わらせるようにしています。
自分がやりたいことに合わせて環境をコントロールすると、自分の意志も無理なくコントロールできるのです。

仕事の効率化、勉強、ダイエット……「三日坊主」を乗り越える技術
ここからは、具体的な場面を想定して、習慣化のコツをお伝えします。社会人が継続できずに悩みがちなことの代表例として、「仕事の効率化」「勉強」「ダイエット」があるのではないでしょうか。これらを三日坊主にせず続けるために生活に取り入れやすい工夫をご紹介します。
・仕事の効率化
仕事を多く抱えているのに、目の前の作業に集中できず悩んでいる人は多いと思います。「仕事をしていても、集中力がすぐ切れてスマホを見たり、ぼーっとしたりしてしまう。本当は今日中に資料を仕上げるはずだったのに終わらなかった」……という経験はありませんか?
冒頭でお伝えしたように、人間は飽きっぽい生き物なので、集中力は長続きしなくて当たり前なのです。ただ、脳の仕組みをうまく使えば、工夫次第で集中力を持続させることができます。人間は、終わりの時間がわかっていると集中力が復活することが研究から明らかになっています。
この本能をいかして、タイマーなどで終了時間を自分に意識させるといいでしょう。その一例として有名なのが、25分の作業と5分の休憩を繰り返すことで集中力を維持させる「ポモドーロ・テクニック」です。疲れたら休憩するのではなく、あらかじめ休憩するタイミングを決めてしまうことで集中力がアップします。
在宅ワーカーは、仕事前に運動することも有効です。10分程度の軽い運動をすると、脳に酸素が送り込まれて集中力をアップさせられます。ランチ休憩の時間もしっかり休みましょう。20分前後の短い昼寝をすると、午後のパフォーマンスが上がります。
仕事中にスマートフォンをつい見てしまう人は、手の届かないところに置くといいですね。休憩時間にSNSなどをチェックする人も多いと思いますが、スマートフォンを見ることは脳のリソースをかなり使う行動なので、疲れが取れないどころか余計に疲労してしまいます。
・勉強
「資格を取ろうと思って勉強を始めた。参考書を買って読み始めたものの、数ページ進んだところで止まっている」……という話もよく耳にします。
これはまさに、新しいことに飽きてしまった状態に他なりません。日々忙しく過ごす社会人が勉強の習慣をつけるには、先ほどご紹介したハビットスタッキングが役立ちます。たとえば「通勤電車に乗ったら、必ず参考書を3ページ読む」「毎朝コーヒーを飲みながら、英単語を5つ覚える」といった工夫は取り入れやすいのではないでしょうか。
行動を起こすまでのアクションの数を減らすことも重要です。部屋のデスクやソファの横などいつも生活している場所に、読みたい本を出しっぱなし、さらに開きっぱなしにしておくことをおすすめします。「本棚から書籍を取り出す」「ページを開く」という2つのアクションが減るので、自然と行動しやすくなるのです。
・ダイエット
間食がやめられず、ダイエットが長続きしない人も多いと思います。食欲は人間の三大欲求のひとつですから、とても強い本能なのです。
だからこそ、食欲を意志の力でコントロールしようとするのは、得策ではありません。取り組みやすい工夫は「気をそらす」こと。食欲ではない他のことに脳のエネルギーを使わせるのです。
たとえば、おでこをトントンとタッピングするだけで食欲を解消できるという、ニューヨークの医師であるウェイルらが行った研究結果があります。ガムを噛む、テトリスのような簡単なゲームを3分間やるなどの単純作業、あるいはランニングや水泳のように同じ動きが続く運動も、食欲から気をそらすことに役立ちます。単純かつ集中できる作業は、作業そのものに脳のエネルギーを使うので、欲求を抑えるために有効なのです。
食欲は毎日湧くものなので、「Aという状況が起きたら、Bという行動をする」というルールをあらかじめ決めておく「イフ・ゼン・プランニング」も活用してみてください。たとえば「間食したくなったら、ガムを食べる」と決め、手の届くところにガムを置いておくのです。
運動が続かない人は、ハビットスタッキングを活用して、朝起きたら着替える服をスポーツウェアにしておくのもいいですね。着替えるという行為は誰もが行うものなので、そこにスポーツウェアを取り入れてしまうのです。
こうした少しの工夫を実践して、習慣化しやすい環境を自分に用意してあげてみてください。
まずは6週間、「脳の仕組み」を使って実践しよう!

習慣化の第一歩は「きちんと準備が整っていなくても、とりあえずやってみること」。人は、行動の後に気持ちがついてくる生き物です。
ある研究によると、新しい行動が日常に定着するには6週間かかるといわれています。最初の6週間を「脳の仕組み」を使って乗り越えれば、その行動をしないと不安に感じるようになるはずです。
三日坊主になるのは、自分の意志が弱いからではないことを理解いただけたでしょうか。今回ご紹介した工夫を生活に取り入れて、新しくやりたいことを継続していってください。
取材・執筆:御代貴子 アイキャッチ・図版:サンノ 編集:モリヤワオン(ノオト)

ブランド名
商品名が入ります商品名が入ります
¥0,000