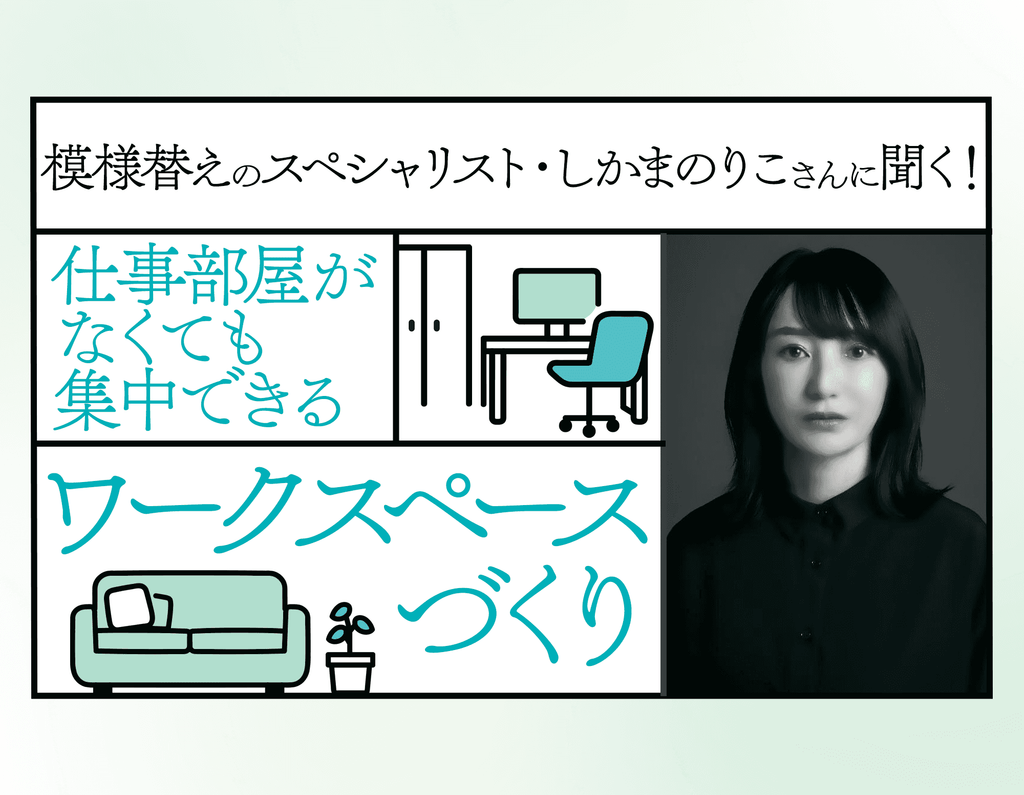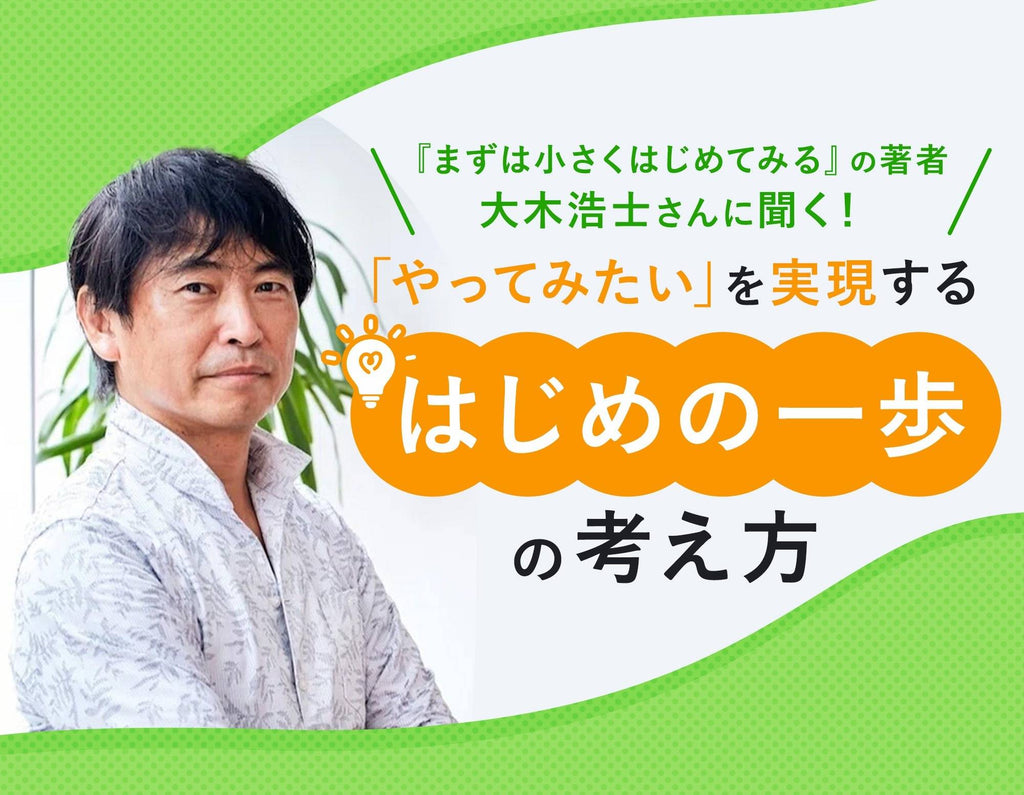親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かした事がある。なぜそんな無闇をしたと聞く人があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。新築の二階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張っても、そこから飛び降りる事は出来まい。弱虫やーい。と囃したからである。
チャットやオンライン会議がメインとなる在宅ワークでは、簡潔ですばやいコミュニケーションや効率性が求められ、それによる疲弊を感じる人も少なくないでしょう。
「このままの働き方でいいの?」「もっと自分らしく働きたい」と感じている人は「ネガティヴ・ケイパビリティ」の考え方を取り入れると良いかもしれません。今回は哲学者・谷川嘉浩さんに、「ネガティヴ・ケイパビリティ」とは何か、在宅ワークでこそ意識したい余白のある思考法を教えていただきました。
ネガティヴ・ケイパビリティとは「モヤモヤを抱えておく能力」
「すぐに返事をする」「なるはやで対応する」とスピード感がある働き方をしている人は多いでしょう。とくにコロナ禍以降は、職場以外でも仕事する人が増え、いつでも、どこでも仕事できるようになりました。
そんな中で注目され始めているのが「ネガティヴ・ケイパビリティ」です。これは、イギリスの詩人ジョン・キーツ(1795年 - 1821年)が作った「不確実さ、謎、疑いの中にいる能力」を記す言葉で、まとまらない状態を許容する態度、「ん?」と立ち止まって考えることを意味します。
これは彼が手紙の中で「文学においてネガティヴ・ケイパビリティが大事だよ」とさらりと書き記した言葉だったのですが、時代を経ていく中でその重要度が多方面から認知されるようになり、現代まで広まってきたと考えられています。じわじわと受け継がれていった言葉といえるでしょう。

とくにここ数年は、技術進歩とともに日に日に判断や意思決定、情報速度がスピードアップしてきました。恋愛を例にしても、現代はいつでもどこでもつながるのが当たり前で、GPSで相手の場所まで把握する人もいるほど……。一方、2000年代初期に流行した携帯小説の『恋空』では、《アシタホウカゴハナソウ》とメールが届き、翌日の放課後までやきもきする主人公の様子が描かれています。こういった悠長さって現代ではなかなかありませんよね。
スピード重視の時代において、人々はせかせかと生きることが主流になっている。そんなメンタリティに対して「速ければいいの?」と一旦立ち止まってみる力が求められているのかもしれません。
スキマ時間を活用しすぎ?
私たちの日常には、コンプレックスを刺激するような情報がそこら中に溢れています。「5分でわかる〇〇」「〇〇の新常識」「成功者だけが知っている〇〇」などの言葉によって、人生にとって必要のないことにまで影響を受け、自分を忙しくしてしまう状況に取り込まれているともいえるでしょう。
哲学者であるフリードリヒ・ニーチェ(1844年 - 1900年)は、「君たちはみんな激務が好きだ。速いことや新しいことや見慣れないことが好きだ」と話しているのですが、これは現代にも通じる言葉ではないでしょうか?
インターネットの普及によって、スキマ時間の10分で「メールの返信をしよう」「会議資料を読んでおこう」「通販で日用品を購入しておこう」ということができるようになりました。良くいえば資本主義社会に適応していると表現できますが、スキマ時間を活用すべきという文化が根付いたことで、何もしないことは悪だと感じてしまうことはないですか。
多くの人たちが「のんびり過ごしたい」「何も考えずに休暇を過ごしたい」と、いつか暇になるために働いているはずなのに、日常がどんどん『激務』になっていく。もちろん効率や生産性が必要な時もありますが、毎日のようにスキマ時間を埋めていく必要があるのでしょうか?
余白をつくり“のんき”に過ごしてみると、意外と「今やらなくてもよかった」と思えることも見えてくるものです。ときには、余白の中から新しい発想も生まれてくることも。
効率重視で生産性の高さを求められる現代において「ネガティヴ・ケイパビリティ」は、効率の悪いことだと思う方もいるかもしれません。でも、効率が重宝されるのは、目的や手段がはっきりとしている場合。もしもあなたの未来が曖昧で、どこに向かっていくか不明瞭ならば、効率や生産性を高めていくだけでは険しい道のりになることは想像できるはずです。
在宅ワークで、軽やかな“孤独”を受け入れる
在宅ワークをしていると「孤独だ」と感じる人もいるでしょう。孤独は悪いものと考える人も多いかもしれませんが、しっかりと孤独を受け入れることが、「ネガティヴ・ケイパビリティ」を身につける上でも必要だと考えています。
歴史的な哲学者たちも、「孤独」についてさまざまな視点から書き残してきました。
友よ、孤独へと逃れよ!
『ツァラトゥストラはこう言った』/フリードリヒ・ニーチェ
孤独を愛さない人間は、自由を愛さない人間にほかならない。
なぜなら、孤独でいるときにのみ人間は自由なのだから。
『幸福について』/ショーペンハウアー
またハンナ・アーレント(1906年 - 1975年)は、「一人であること」は〈孤立〉〈孤独〉〈寂しさ〉の三つの様式にわけられると述べています。それぞれの意味を考えておきましょう。孤立は誰にも邪魔されない状態、孤独は自己との対話(=思考)する状態、寂しさは他人といる時に感じる感情で自分以外の人に依存している状態を示します。
つまり物理的に人との接触を絶つことではなく、自分が生きている社会や人間関係からある程度距離を置きながら、思考し続けることが〈孤独〉です。在宅ワークというある種〈孤立〉の状態は、自己との対話、つまり〈孤独〉にもうってつけといえるのではないでしょうか。
注意してほしいのが、思考し続けていく中で自己愛が高まり、ナルシシズムに傾き自己陶酔してしまうのは哲学者たちが考えている〈孤独〉とは少しズレてしまうということです。哲学者たちが考える〈孤独〉とは、多様な価値を受け入れて、自分の中で軽やかに消化していける状態になること。周りに左右されることなく自分の時間を楽しめる、味わえる、そんな状態とも言えるでしょう。
<「軽やかな孤独」を持つ人って、こんなキャラクター>
・『新世紀エヴァンゲリオン』に登場する、加持リョウジ
・『葬送のフリーレン』の主人公、フリーレン
・ムーミンの友だちで旅人の、スナフキンちなみに、容易につながれるようになった現代人は〈寂しさ〉に引っ張られやすい状態にあります。在宅ワークでも、他者の仕事ぶりをチャットなどで見ることで「私だけ効率的に働けていないのでは?」「他の人より遅れているかも……」と不安が先行してしまうかもしれません。〈孤独〉を受け入れ、周りと比べることもなく、心軽やかな在宅ワークを意識してみましょう。
自分の中にある「複数の声」に耳を傾けてみよう
とはいえ、「ネガティヴ・ケイパビリティ」が大切だ!さぁ孤独になろう!と言ってもなかなか難しいもの。では、どうしたらいいのか? おすすめなのが「一者の中の二者(the two-in-one)」を取り入れる方法です。自分の中に複数の他者がいて、その声に耳を傾けながらあーでもない、こーでもないとぐるぐる考え続けること。自分を客観的に見る自分以外の存在を意識するだけで、軽やかな孤独を育むことができるようになるでしょう。

毎日がスピーディーに過ぎてしまうと、自分を客観的に見る時間もなくなってしまいます。答えを出すことを急がず、モヤモヤを抱えながら生きていく。自分の中に「よどみ」を持つことが、自分自身を見つめなおすきっかけになるはずです。
最近セカセカしているな、なんだか社会に流されているなと感じたら、「ネガティヴ・ケイパビリティ」を思い出してみてください。生活に余白をつくり、〈孤独〉とうまく付き合っていく中で、自分の中にいる他者からヒントをもらえるようになるでしょう。
ライター:つるたちかこ アイキャッチ・図版:サンノ 編集:モリヤワオン(ノオト)

ブランド名
商品名が入ります商品名が入ります
¥0,000