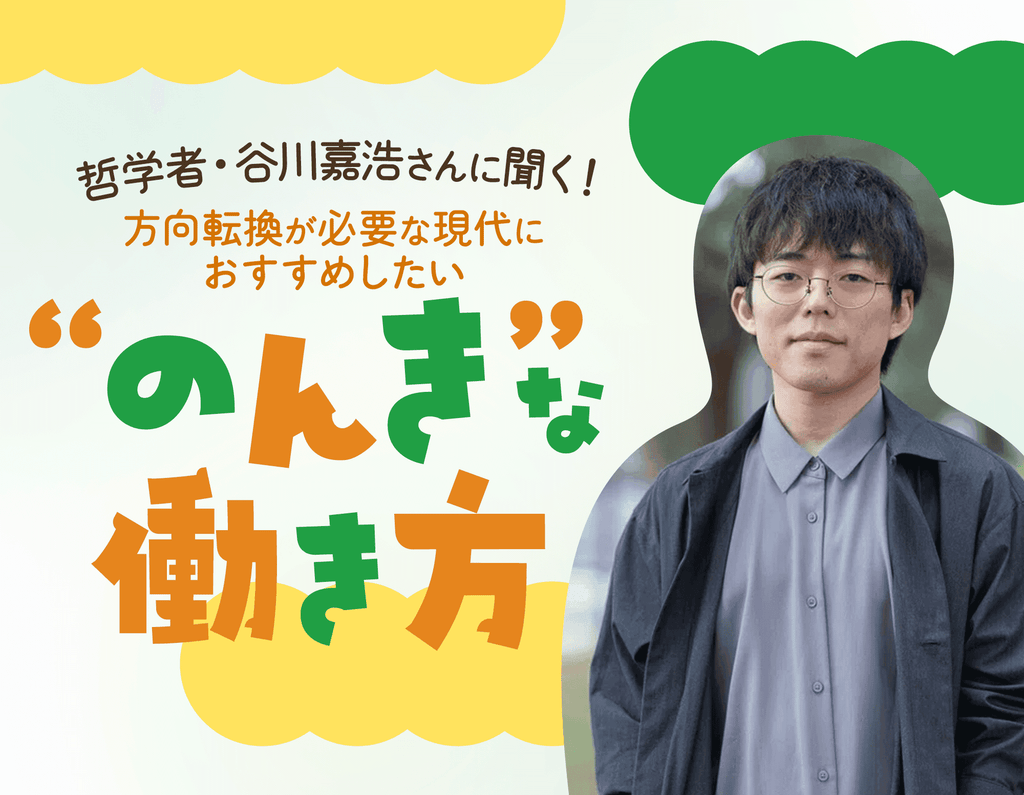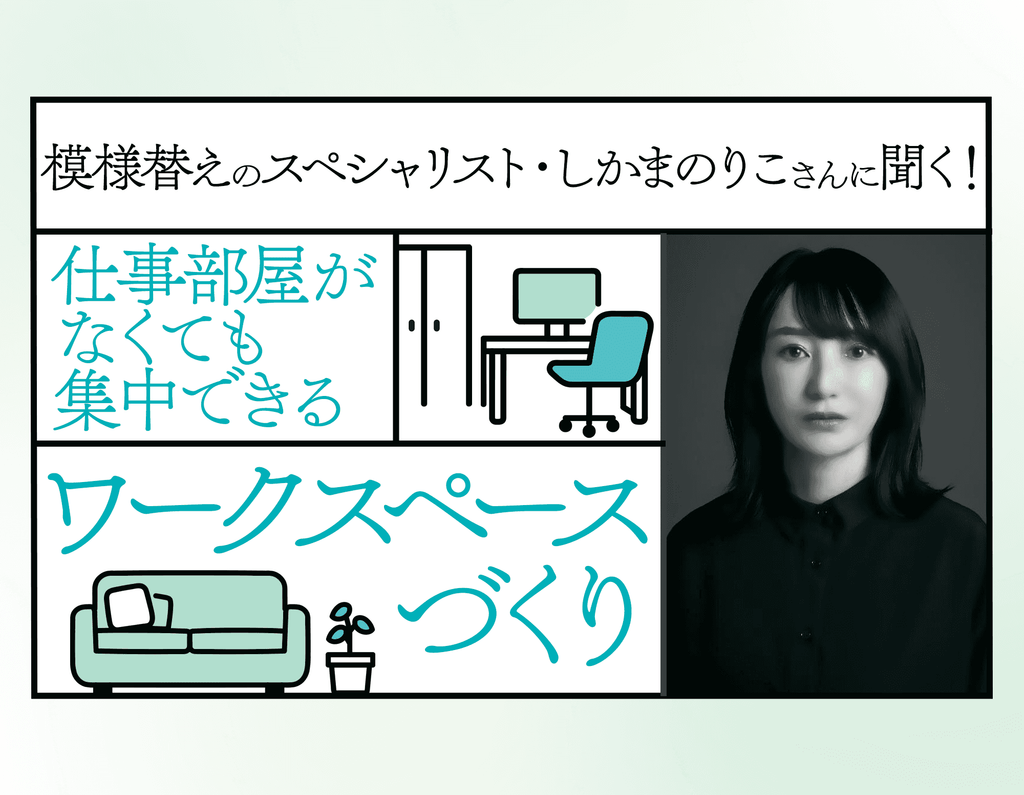親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かした事がある。なぜそんな無闇をしたと聞く人があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。新築の二階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張っても、そこから飛び降りる事は出来まい。弱虫やーい。と囃したからである。
コロナ禍を経て、多くの会社で導入されたリモートワーク。通勤の必要がなく、自宅で業務ができるメリットがある一方、チームメンバーの顔が見えず、周りの人に頼るハードルが上がってしまっています。
「仕事の量が多すぎるけれど、誰かにお願いするのも気が引けるな……」「みんな忙しそうで業務の相談がしにくい……」と悩みながらも人に頼ることができず、「じゃあ、自分でやればいいか」とひとりで業務を抱え込んでしまう人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、周りに助けを求めるビジネススキル「ヘルプシーキング」を提唱する株式会社NOKIOO・小田木朝子さんに、リモートワーク時代に一人ひとりが意識したい「頼る技術」についてお話を伺いました。
ヘルプシーキングは、「チーム」で成果を出すためのビジネススキル
こんにちは、小田木朝子です。人材育成・組織開発事業を手がける株式会社NOKIOOで取締役をしています。
今回ご紹介する「ヘルプシーキング」という考え方に出会ったのは、仕事も育児も家事も自分ひとりで抱え込んでしまい、もう仕事は続けられないかもしれない……と深く悩んでいた頃でした。
自分自身がヘルプシーキングを実践することで、仕事の進め方が劇的に変わった経験を生かしながら、研修のプログラムを開発して提供したり、発信活動をしたりしています。
ヘルプシーキングとは、直訳すると「助け(help)を、探している(seeking)」。周囲に援助や支援を求める行動のことです。
「助けを求める」というと「あの人は、人に頼るのが上手いよね」など、性格のタイプ論的に語られがちですが、ヘルプシーキングはビジネススキルです。つまり、誰でも学んで実践していけば、活用できる技術といえます。
ビジネススキルは「そのスキルを使うと成果が上がる」から活用するもの。つまり、「周囲に援助や支援を求める行動」ができれば「チームの成果が上がる」のです。
であれば、ヘルプシーキングもどんどん使いたいところですが、リモートワークにおいて難しいのは「相手が見えない」こと。見えないから、周囲に助けを求めたいのに気が引けてしまう。
「上司も忙しそう」などと勝手に推察してしまったり、自分から助けてほしいと口にしないからいつまでも気づいてもらえなかったり……ということはありませんか?
こうならないようにするには、困ってから初めて助けを求めるのではなく、平常時から「困っていてもいなくても、みんなで連携すること」が重要です。
チームメンバーを見渡しても、得意分野やプライベートも含めた抱える事情、起こりうる不測の事態も違うはず。だからこそ、一人ひとりが意識して、平常時から連携することが大切なのです。
ヘルプシーキングは、チームで成果を出すために、周囲に助けを求めるビジネススキルであること。そして、緊急事態にだけ使うスキルではないことをまず理解していただければと思います。

どうして頼るのが苦手? 自分を俯瞰してみよう
前段でもお話した通り、正しい頼り方を身につければ、チームの成果は上がっていきます。それでも、「助けを求めることは、難しいことだ」と思ってしまう人はいるのではないでしょうか。
まずは、その固定観念を解きほぐすために、なぜ頼るのが苦手なのか、「自分の心理傾向」を知ることから始めるのをオススメします。
人に頼るのが苦手といっても、その理由はさまざまです。たとえば、
・迷惑をかけたくない
・相手が忙しそうなので、遠慮してしまう
・人に頼ってしまったら自分が成長できない
・仕事ができない人だと思われたくない
・自分がやった方が早い
といったことが挙げられます。この中で、あなたの気持ちに近いものがあるか考えてみましょう。
まずは、自分の傾向を客観的に知るだけでいいのです。良い・悪いがあるわけではないので、反省する必要はありません。
なぜ人に頼ることへブレーキをかけてしまうのかを知っておくことで、自分の気持ちをコントロールしヘルプシーキングを実践しやすくなります。たとえば「今、無能だと思われたくないと強がっているな」「相手は忙しいだろうと気を遣っているな」などと、俯瞰して対処できるようになるのです。
あるいは、周りの人に「私、こういうブレーキがかかりやすいんです」と言っておくのもいいですね。ブレーキがかかっているとき、周囲がサポートしやすくなります。

下手っぴな「頼る」はもうやめよう! 人に頼るのは、迷惑をかけることではない
頼るのが苦手な自分を乗り越えるためのもうひとつの観点は、「人に頼る=迷惑をかける」という捉え方をやめることです。
仕事を抱え込むより、早い段階で開示してもらった方が結果的にチームは助かります。困らない限りは自分でやる、あるいはギリギリまで自分でがんばってダメなら助けを求めるのは、「下手な頼り方」なのです。
なぜ「下手」かというと、困ったときを想定してチームに情報共有をしていないから。どうしようもなくなってから人に助けを求めると、その頃には問題が深刻になっていて、打てる手段が限られてしまいます。早い段階からチームで対処できていたら、やれることがもっとあったかもしれませんよね。
それに、早い段階で人に頼るからこそ、助けを求める心理的なハードルが下がりますし、周囲も助ける余力があるのです。
また、自分ひとりで仕事を抱え込む癖がついていると、逆に他のメンバーへの関心をもちづらくなるという弊害もあります。すると、周囲のヘルプシーキングに応えられず、チームの成果が出せなくなる悪循環に陥るのです。
ギリギリになってから頼ることで他者の負担が大きくなる「下手な頼り方」ではなく、チームの成果に繋がりやすい頼り方をして、「頼る」ことへの認識をアップデートしていきましょう。

そして、ヘルプシーキングのポイントは「どう助けてほしいか」をきちんと言葉にして伝えること。「察してほしい」はNGです。
たとえば、業務が追いつかず毎日残業している人。残業になっている理由には、「業務の量そのものが多い」とか「スキルが習熟していないから時間がかかる」など、さまざまなものがあります。その理由を伝えずに、ただ「助けてほしい」と丸投げしてしまうと、助ける側がどうアプローチしていいかわからず、困ってしまいますよね。
ここでも大切なのは、チームの観点です。「チームとして成果を出すために、どう助けてほしいか」を伝えることが、実践のポイントです。
ヘルプシーキングを実践しやすくするために、普段から会話をしよう
チームリーダーや上司の方は、メンバーがヘルプシーキングをしやすくするための環境づくりを見直してみましょう。おすすめなのが、普段から定期的にチームで情報共有する場をつくることです。たとえば、週1回は全員で集まり、何を相談してもいい時間を設けるといったことがあげられます。
私のチームメンバーはリモートワークで業務に当たっているのですが、毎朝15分、オンラインで今日の予定や仕事の状況を共有しています。15分だと負担もかかりませんし、「わざわざミーティングするほどではないけれど、共有しておいたほうがよさそうなこと」が言いやすいんです。
「子どもが体調を崩しそう」といった「起きかけていること」もこの場で伝えられますし、自分以外のメンバーの状況も知っておくことでお互いを助け合いやすくなるメリットがあります。
リモートワークだからこそ、こうした時間を大切にしてほしいと思います。会議の前後やお昼休みなどに、ちょっとした会話ができる出社時とは違い、リモートワークでは雑談の時間が取りづらいものです。だからこそ、情報共有を「仕組み」にしておくのがオススメです。

一方、上司にこうした情報共有に対する問題意識がないことに悩んでいるメンバーは、まずは上司と1対1で、週1回15分でもいいので定期的に話をする時間をもらえるよう、お願いしてみるのも一案です。これも、問題が起きているときではなく平常時に依頼するといいでしょう。
普段からコミュニケーションを取って、お互いの状況を知っておくことは、ヘルプシーキングを実践する前提条件となります。「ミーティング未満」のコミュニケーションは、思っている以上に大切なのです。
ヘルプシーキングの視点から、お悩みにアドバイス
ここでは、ヘルプシーキングを用いて、具体的な悩みをどう捉え、解決していくべきかをご紹介します。
お悩みその①
業務が追いつかず毎日残業。でも、上司に助けを求めるハードルが高いんです。
「上手に頼ることは、みんなのためになる」という意識を念頭においておきましょう。限界を迎えてからの相談は自分にとっても相手にとっても負担です。手遅れになる前に、早い段階でチームに状況をシェアして。相談のときは、「自分がどう助けてほしいか」を明確にして伝えられればGOODです。そうすればチームも問題解決に向けて、スムーズに動くことができます。
お悩みその②
育児との両立で早退が多い日々。メンバーへ感謝を伝えているつもりだけど、嫌な気持ちにさせているかもなあ……。
相手の気持ちを想像してしまうクセを見直してみて。とくに、メンバーの様子がわからないリモートワークでは、相手の状況や考えを想像してしまいがちです。想像を膨らませて過度に気をつかうと、パフォーマンスも上がらなくなってしまいます。「こう思われている」と決めつける前に、雑談や業務報告の機会をうまくつかって、相手の気持ちや考えを知れるといいですね。
お悩みその③
部下に追加で業務をお願いしたい。でも、文面だと温度感が伝わりにくく、苦痛だと思われてしまうかも……。
リモートワークではテキストコミュニケーションが多くなりがちですが、オンラインでもよいので、対面に近いコミュニケーションを取り入れてみてください。文面だけのコミュニケーションは一方通行になりやすく、とくに上司の指示は拒否しにくいもの。私も、チームのメンバーとはテキストとオンラインミーティングを組み合わせてコミュニケーションをとっています。「対話」が大切ですよ。
悩みは「自分ごと」から「チームごと」に置き換えて考えると、みんなハッピー
仕事を抱え込むことは、自分のためにもチームのためにもなりません。日常的に情報共有をしながら、チームで連携して成果を出すことが大切です。
ヘルプシーキングのはじめの一歩として、「一人称の判断」をやめることから始めるといいのではないでしょうか。自分の担当業務で起きた問題は、「自分自身の問題」ではなく「チームの問題」です。
ひとりで悩むのではなく、早い段階でヘルプシーキングをすることで「自分ごと」から「チームごと」にして、チームとしてどうしたら解決できるかを全員で考え、成果を上げていきましょう。
小田木朝子
株式会社NOKIOO 取締役/経営学修士
2011年にNOKIOO創業メンバーとして参画。事業推進、人・組織に関するコンサルティングを担う。組織と個人の持続的な発展を実現する”これからのチームワーキング”を体系化し、企業の組織開発・人材育成を支援。組織の枠を越えた「越境型人材育成プログラム」として、2020年に「スクラ」を事業化。
明日の景色を変える「仕事サプリ」(Voicy):https://voicy.jp/channel/1240
ライター:御代貴子 アイキャッチ・図版:サンノ 編集:モリヤワオン(ノオト)

ブランド名
商品名が入ります商品名が入ります
¥0,000